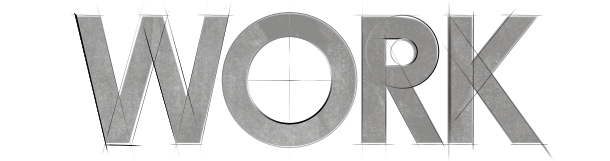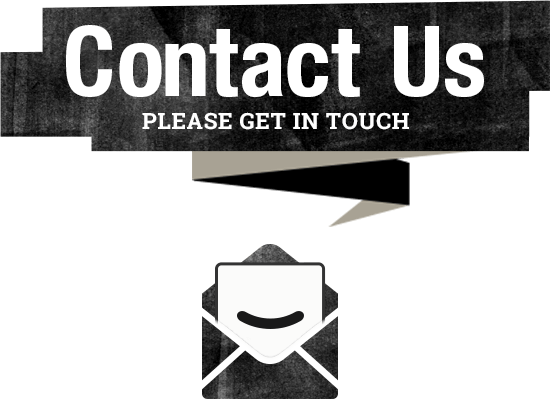【徹底解説】チャットボットとは?機能・導入メリット・作り方まで詳しく解説

近年、生成AIの進化によりチャットボットは大きく変化を遂げています。
かつてはFAQ対応や定型的な案内が中心でしたが、今では自然な会話や複雑な問い合わせにも対応でき、マーケティング・営業支援などビジネスの幅広い場面で活用されるようになりました。情報があふれる時代に「必要な情報を必要な人へ届ける」仕組みとして、チャットボットはAI時代のビジネスに欠かせない存在となりつつあります。
本記事では、チャットボットの基本や歴史から、導入メリット、活用事例、さらには選び方までを徹底解説します。
- チャットボットを導入したいが、何から考えればよいのか分からない
- どのサービスを選べば効果が出るのか知りたい
このような悩みを持つ方にとって、疑問を解消し次の一歩を踏み出す手がかりになれば幸いです。
記事の最後には我々クーシーが考える「チャットボット活用の未来」にも触れていますので、ぜひ最後までお読みください。
チャットボットとは?
チャットボットとは、ユーザーとの会話(チャット)を自動で行うプログラムの総称です。iPhoneの「Siri」や「ChatGPT」など、一度は使ったことがある方も多いのではないでしょうか。
近年は、専門的な知識がなくても簡単にチャットボットを作成できるサービスが登場し、企業のWebサイトやSNS、カスタマーサポートなど、さまざまな場面で活用が広がっています。
主な機能としては次のようなものがあります。
- 情報提供・案内:FAQへの自動応答や商品・サービスの紹介
- 顧客対応:問い合わせへの一次対応やトラブル対応
- 予約・申し込み管理:予約受付や資料請求の対応
さらに近年は生成AIの進化により、従来の機能に加えてユーザー特性に応じたパーソナライズ対応や、あらかじめ用意されていない抽象的な質問への柔軟な回答も可能になるなど、成長著しい注目の分野です。
チャットボットの現代までの歩み
チャットボットの歴史は、1966年にMIT(マサチューセッツ工科大学)で誕生した「ELIZA」から始まります。
ELIZAはユーザーの言葉に含まれるキーワードを拾い、あらかじめ用意された応答を返すだけのシンプルな仕組みでしたが、人と機械が会話できるという可能性を示した画期的な存在でした。
その後1990年代には、より複雑なルールを組み込んだチャットボットが登場し、応答の幅は広がりましたが、決められたルールに従って応答するルールベースでは想定外の質問や文脈の理解に限界があり、実用の面で課題が残っていました。
こうした状況を大きく変えたのが、生成AIの登場です。大量のデータから自ら学習できるようになったことで、より柔軟で自然な会話が可能となりました。さらに2016年には、LINEやFacebookメッセンジャーが開発用APIを公開したことで、企業での導入が一気に加速します。
現在では、生成AIを基盤にしながら、ルールベースの手法を組み合わせたハイブリッド型が主流となり、多様で高度な対話が実現されています。
チャットボットの種類と仕組み
チャットボットは主に、「シナリオ型」「AI型」「ハイブリッド型」の3つに分類されます。それぞれの特徴と仕組みを見ていきましょう。
シナリオ型(ルールベース型)
シナリオ型チャットボットとは、言葉の通りあらかじめ用意された会話の流れ(シナリオ)に沿ってやり取りを行う仕組みです。対話型のシミュレーションゲームを思い浮かべるとイメージしやすいかもしれません。
具体的には、「ユーザーに選択肢を提示し、回答に応じて枝分かれしていくタイプ」と、「質問のキーワードを認識し、用意してある回答を提示するタイプ」などがあります。
枝分かれタイプ
1. 「お問い合わせ内容を選んでください。」
①営業時間について
②アクセスにてついて
③料金について
2. 「どちらへのアクセスについての情報をお探しですか?」
キーワード認識タイプ
Q:料金体系を教えてください。(ここで「料金」というキーワードを認識)
A:料金に関してはこちらをご参照ください。
シナリオ型の特徴には以下のようなものが挙げられます。
- 正確な回答ができる
- 導入コストが低い
- 想定外の質問に答えられない
- シナリオ準備の負担が大きい
シナリオ型の最大のメリットは導入コストの低さです。複雑な開発を必要とせず、月5,000円程から利用できるサービスも存在しています。
しかしながら、回答の柔軟性や導入のしやすさではAI型に劣ります。想定外の質問に対応できないため、問い合わせ内容がある程度限定されているケースや、大量のシナリオを準備できる場合に適した仕組みといえるでしょう。
AI型
AI型チャットボットとは、AIがユーザーの入力内容や文脈から要望を理解して回答を導き出す仕組みです。iPhoneのSiriとの会話をイメージしていただくとわかりやすいかも知れません。
シナリオ型との大きな違いは、異なる表現でも意味を汲み取ることができる点です。具体的には下のようにそれぞれ異なる表現をしていても、「パスワードの確認、もしくは再発行がしたい」という意味で解釈してくれます。
全て「パスワードの確認、もしくは再発行がしたい」と解釈してくれます。
・ パスワードを忘れた場合どうすればいいですか?
・ パスワードを忘れました。
・ パスワードを作り直したいです。
AI型の特徴には以下のようなものが挙げられます。
- 複雑な問い合わせや想定外の質問にも対応可能
- シナリオを作り込まなくて良い
- 誤回答のリスクがある
- 導入コストが高い
シナリオ作成が不要であることや、柔軟な会話が可能である点はAI型の大きなメリットです。自然な会話の流れで、膨大な情報の中から最適な回答を提示できるため、顧客満足度の向上にもつながります。
一方で、学習データの整備やシステム導入にコストがかかり、誤回答のリスクもゼロではありません。そのため、シナリオ作成をする余裕がない場合や、幅広い質問に対応する必要がある場合に適していると言えるでしょう。
ハイブリッド型
ハイブリッド型チャットボットとは、シナリオ型とAI型の両方を組み合わせた仕組みで、クーシーが提供するチャットボットもこのハイブリッド型を採用しています。シナリオ型の「想定外の質問に回答できない」という欠点と、AI型の「誤回答の可能性がある」という欠点を両方補うタイプとして注目を集めています。
参考
ハイブリッド型の大きな特徴は、機能の自動切り替えが可能である点です。定型的な質問にはシナリオ型で正確に対応し、想定外の質問や複雑な問い合わせにはAIが柔軟に応答するため、安定性と自然さを両立できます。
具体的には、次のような動きをします。
シナリオ対応の例
Q: 「営業時間を教えてください。」
A :「当店の営業時間は9:00~18:00です。」
AI対応の例
Q: 「来週の昼に家族で行く場合、混雑を避けるおすすめの時間は?」
A: 「比較的空いているのは14時以降です。ご家族での来店におすすめです。」
ハイブリッド型の特徴には以下のようなものが挙げられます。
- 安定性と柔軟性を両立できる
- シナリオ準備の負担が軽い
- 機能切り替えの基準を設定する必要がある
- シナリオ修正と学習データの更新の両方が必要
ハイブリッド型の最大のメリットは、誤回答を減らしながら柔軟な対応も実現できる点です。シナリオ部分で確実性を担保しつつ、AI部分で幅広い会話をカバーできるため、ユーザー体験の向上と業務効率化に直結します。
一方で、シナリオとAIを切り替えるルール設計や運用体制の整備が必要で、導入コストや管理工数がシナリオ型より高くなる傾向があります。そのため、FAQや予約などの定型処理も必要だが、複雑な質問への対応も求められるケースに最適な仕組みといえるでしょう。
Web担当者が知っておくべき!チャットボット導入の4つのメリット
次に、チャットボットを導入することのメリットを具体的に見ていきましょう。
近年、多くの企業が自社Webサイトにチャットボットを導入しています。その背景には、カスタマーサポートの自動化や業務効率化といった実務的な理由だけでなく、顧客体験(UX)を改善する重要な手段として注目されていることがあります。Web担当者としては、導入効果を正しく理解しておくことが欠かせません。
ここでは、実際にチャットボットの導入支援や運用を行っているWeb制作会社クーシーが、導入の4つの主要なメリットを解説します。
1. 24時間365日対応で顧客満足度が向上
チャットボットを導入することで、営業時間外や休日でも問い合わせに対応できるようになります。
例えば「商品の在庫を確認したい」「キャンセル方法を知りたい」といった質問は、ユーザーが思い立った瞬間に解決できるのが理想です。これまでなら翌営業日を待つ必要があったものが、即時に解決できることで顧客満足度は格段に向上します。
特にECサイトや宿泊予約サービスなど「夜間や休日にアクセスが集中する業種」では大きな効果を発揮するでしょう。人員を増やさずに「いつでも対応できる窓口」を持てることは、企業にとって大きな強みとなります。
2. 問い合わせ対応の負担軽減とコスト削減
チャットボットを導入することで、よくある質問や定型的な問い合わせを自動化できます。これによりサポート担当者の対応件数を大幅に減らすことができ、人件費や外注費、さらには残業代といったコストの圧縮にもつながります。
例えば、100件の問い合わせのうち7割が「営業時間」「料金」「ログイン方法」などの簡単な質問だった場合、それらをチャットボットに任せるだけで担当者の負担は大幅に軽減可能です。
また、この効果は規模の大きい企業であるほど顕著に表れます。顧客数が増えれば増えるほど問い合わせ件数と対応のための人員は増えていきますが、チャットボットを活用すれば、人を大幅に増やさずに多くの問い合わせに対応できるため、省人化の効果が特に高まります。
結果として、サポート体制の効率化だけでなく、企業全体のコスト構造の改善にもつながります。
3. UX改善でコンバージョン率が向上
チャットボットは、ユーザーが求める情報をすぐに提示するだけでなく、顧客体験(UX)を高めることでコンバージョン率の改善にもつながります。
例えば、ユーザー属性や条件を尋ねて担当者へ即時に接続したり、チャット上でアポイント調整や予約を完結させたりと、スムーズな導線を提供できるのが特徴です。ECサイトでは「おすすめ商品」や「割引クーポン」を提示し、決済ページで特典を案内することで、購入完了率を押し上げる効果も期待できます。
また、初来訪者にはサービス概要をまとめたガイドを提示することで理解を促し、離脱を防ぐ役割も果たします。
このように「商品推薦」「クーポン提示」「アポ調整」「EFO(入力支援)」「チャット内決済」といった仕組みを組み合わせれば、ユーザー体験は自然に向上し、最終的にはコンバージョン率の大幅な改善へと結びつくでしょう。
4. 問い合わせデータの蓄積により顧客ニーズを把握
チャットボットは、ユーザーとの会話を自動的に蓄積できるため、問い合わせ内容を分析することで「よくある質問」や「つまずきやすいポイント」を把握できます。これにより、顧客ニーズをデータとして可視化できるのが大きな強みです。
例えば、ECサイトで「配送状況」に関する質問が多ければ導線改善が必要だと分かりますし、SaaSで「料金プランの違い」に関する問い合わせが多ければ説明を分かりやすく修正するといった施策に活かせます。
このように、チャットボットは単なるサポートツールにとどまらず、商品改善やマーケティング戦略に役立つ顧客理解の基盤としても機能します。
チャットボットの具体的な活用例
ここからは、実際にチャットボットがどのように活用されているのかを具体的に見ていきましょう。
単なる問い合わせ対応にとどまらず、マーケティングや社内業務の効率化、さらにはインバウンド対策まで、想像以上に幅広いシーンで活用されていることがわかると思います。
ユーザー対応
一番わかりやすいのは、お客様からの問い合わせ対応です。
例えば「営業時間を知りたい」「配送はいつ届く?」といったよくある質問に、すぐ答えてくれる存在として活躍します。宿泊施設なら「チェックインは何時から?」、ECサイトなら「返品はどうすればいい?」など、ちょっとした疑問をその場で解決できるので、ユーザーにとってもストレスがありません。
担当者が電話やメールで同じ質問に繰り返し答える必要もなくなり、双方にとって大きなメリットがあります。
マーケティング・営業支援
チャットボットは、単なる自動応答の枠を超えて、マーケティングや営業の場面でも活用が進んでいます。
マーケティングでは、ユーザーとの会話を通して「どんなサービスに興味があるのか」「購入を検討しているのはいつ頃か」といった情報を自然に引き出すことができ、こうして集めたデータは、ユーザーニーズを正確に理解する手がかりとなり、次の施策やキャンペーンを考えるうえで大きなヒントになります。
営業シーンでは、チャットボットが会話の中で得た情報を整理し、条件に合った段階で担当者につなげることなども可能です。例えば「予算感」や「導入時期」をあらかじめ把握した状態で担当者が引き継げば、商談はよりスムーズに進みます。ユーザーにとっても「ちょうどいいタイミングで人と話せた」という心地よい体験につながるでしょう。
つまりチャットボットは、マーケティングではデータを集めて施策を支える存在に、営業では商談のきっかけをつくるアシスタントに。それぞれの場面で、人に寄り添うような役割を果たしてくれています。
社内ヘルプデスク
実は社内での利用も非常に便利です。
「パスワードを忘れたときは?」「経費精算の申請方法は?」など、社員から毎日のように寄せられる質問にチャットボットが答えてくれるので、担当部署の負担がぐっと減ります。
規模の大きな企業では、チャットボットを導入して社内問い合わせの数が半減したという例も珍しくなく、バックオフィスの負担軽減に大きく貢献しています。
多言語対応・インバウンド対策
訪日観光客の増加や海外ユーザーの利用を見据え、チャットボットの多言語対応も重要になっています。
自動翻訳機能を活用すれば、日本語で登録したFAQを英語や中国語などに切り替えて案内できるため、外国人ユーザーも安心して利用することが可能です。
また、ホテルや観光施設では「空港からのアクセス方法」や「チェックイン手順」を多言語で即答でき、言葉の壁を越えたスムーズな接客も可能になるため、観光施設や小売店など、インバウンド需要のある業種にとっては大きな武器になるでしょう。
チャットボットの導入事例
ここまでチャットボットのメリットや活用の具体例を解説してきました。
ここでは、実際にチャットボットを活用して成果を上げている企業の事例を紹介します。
クレディセゾン:カスタマーサポートと社内対応の両面で活用

クレディセゾンでは、2017年にシナリオ型対話機能を備えたチャットボットを導入し、カード会員からの問い合わせ対応を自動化しました。これにより、電話やメール対応の負担を軽減し、ユーザーが24時間いつでも情報を取得できる環境を整備しています。
さらに、社内向けには内製開発したFAQシステムと連携した「アシストくん」を導入。社員からの問い合わせにもチャットボットが対応することで、業務のスムーズ化と生産性向上を実現しています。
損保ジャパン:24時間対応で顧客サポートを強化

損保ジャパンでは、2020年1月よりAIチャットボット「BEDORE Conversation」を導入。まずは海外旅行保険【off!】の問い合わせ対応から開始し、その後自動車保険・火災保険などへ順次拡大しています。
この取り組みにより、24時間365日の受付が可能になり、電話窓口が開いていない時間帯でも保険の問い合わせができる環境を構築しました。また、LINE上のチャットボットも活用し、保険金請求手続きをオンラインで完結できる仕組みを導入しています。
チャットボットの作り方
チャットボットについて理解も深まってきたところで、実際に導入する際のステップを解説していきます。
通常チャットボットの導入は「自作する場合」と「外部サービスを利用する場合」のどちらかの方法で行いますが、本記事では「外部サービスを利用する場合」を解説していきます。
以下のステップでチャットボットの導入は進めていきます。
- 目的の整理
- 要件定義
- サービスの比較・選定
- シナリオの準備・学習データの収集
- 設計と構築
- テストと公開
- データ更新
1. 目的の整理
最初に行うべきは「なぜチャットボットを導入するのか」を明確にすることです。
問い合わせ対応の効率化が目的なのか、売り上げ増加に繋げたいのか、顧客満足度を上げたいのか。ここを曖昧にしてしまうと、この後に続く要件定義や、サービスの選定、シナリオ設計やデータ準備の段階で方針がぶれてしまい、費用の増加やリソース配分の失敗につながります。
2. 要件定義
目的が整理できたら、次は「どの機能が必要か」を考えます。
FAQ対応だけで足りるのか、それとも外部システム連携や予約機能が必要なのか。対象ユーザーや運用体制をイメージしながら目的に沿って検討するのがポイントです。
要件定義が曖昧だと、後の設計やサービス選定で迷走する原因になるため、慎重に進めるようにしましょう。
3. サービスの選定・比較
チャットボットのサービスは数多く存在しており、低コストでシンプルに始められるものから、AIを活用した高機能なものまで幅広いのが実情です。
比較・選定の詳しい方法については次の章で解説いたします。
4. シナリオの準備・学習データの収集
シナリオ型の場合は、どんな質問が多いかを事前にリスト化し、それぞれへの回答を準備します。AI型の場合は、マニュアルやFAQ、過去の問い合わせ履歴を学習データとして整理しておく必要があります。
ここを丁寧に行うかどうかで、チャットボットの「回答の質」が大きく変わります。ユーザーが「役に立った」と感じるかどうかは、この段階にかかっていると言っても過言ではないので、丁寧に進めるようにしましょう。
5. 設計と構築
この段階では、チャットボットを「実際に使ってもらう形」に仕上げていきます。
まずは会話の流れを設計し、ユーザーが迷わず目的にたどり着けるようにシナリオや分岐を整えます。あわせて、チャット画面のデザインや選択肢ボタンの有無など、UI/UXの設計も行なっていきます。
さらに、FAQや学習データの登録、予約システムやCRMなど外部サービスとの連携といった機能面を構築し、最後に、有人対応に接続するタイミングやログの収集方法など、運用を見据えた仕組みを組み込むことで、実用性の高いチャットボットが完成します。
6. テストと公開
完成したらすぐ公開したくなりますが、ここでのテストが非常に重要です。
想定した通りに動くか、誤回答がないか、ユーザーの立場に立って細かくチェックします。小さく公開して一部のユーザーに使ってもらい、フィードバックを得て改善するのも効果的でしょう。
テストを軽視すると、不具合や使いづらさがそのまま広がってしまうリスクがあるため、入念に行うことを心掛けましょう。
7. データの更新
チャットボットは公開して終わりではありません。新しい商品が出ればFAQを追加し、回答に誤りがあれば修正していく必要があります。
定期的な改善を重ねることで、チャットボットは「育っていく」存在です。ここを怠ると「役に立たない」と感じられてしまうので、運用体制を整えて継続的に改善することが成功の鍵です。
チャットボットを選ぶ際の比較ポイント
実際にチャットボットを導入しようとした時、どのサービスにしようかと必ず迷うことになると思います。
価格や機能だけで判断するのではなく、運用体制や導入の目的と照らし合わせながら総合的に判断するようにしましょう。
主な比較ポイントは下の5つになります。
- シナリオ型かAI型か
- 導入後の運用サポートはしてくれるか
- 分析・レポート機能はあるか
- コストパフォーマンスに優れているか
シナリオ型かAI型か
まず検討すべきは、シナリオ型にするかAI型にするかです。
よくある質問や予約受付など、問い合わせ内容がある程度決まっている場合にはシナリオ型で十分でしょう。一方で「ユーザーが自由に質問する場面が多い」「想定外の問い合わせにも対応したい」といったケースでは、AI型が力を発揮します。
この判断を誤ると「ユーザーにとって役に立たない」か「企業にとってコストに見合わない」か、どちらかの失敗につながるリスクが高くなるため、注意が必要です。
例えばシナリオ型を選んだのに、実際の質問が自由度の高い質問ばかりだった場合、チャットボットは回答することができず、導入したのにも関わらずユーザーに使ってもらえない可能性があります。逆にAI型を導入したのに、実際は単純なFAQ対応が中心だった場合、無駄にコストが膨らむだけで、投資対効果が下がってしまいます。
強みを持つ領域はどこか
各サービスには強みを持つ領域があり、自社の課題とサービスの強みがかみ合っているかをしっかりと確認するようにしましょう。
各サービスが強みを持つ領域には、以下のようなものがあります。
- 顧客対応・体験の改善
- マーケティング支援
- 営業支援
- コンバージョン支援
- 社内業務の効率化
- 業界特化(EC/小売、金融、保険、医療、不動産、旅行など)
このように、各サービスはそれぞれの強みを持っています。だからこそ、自社の課題が「売上アップ」なのか「サポート効率化」なのか、あるいは「見込み顧客の獲得」や「商談化の促進」なのかを整理したうえで、それに合った強みを持つサービスを選ぶことが重要です。
逆に、課題とサービスの強みがかみ合っていないと、コストだけかかって十分な効果が得られないという残念な結果になりかねないので、注意が必要です。
導入後の運用サポートはしてくれるか
チャットボットは公開後の改善が欠かせません。新しい質問や想定外の問い合わせが出てきたときに、すぐに対応できるかどうかでユーザーの満足度は大きく変わるからです。
運用を自社だけで抱えると、担当者が日々の問い合わせを分析してFAQを修正したり、誤回答の原因を探って改善したりと、予想以上に工数がかかります。特に利用規模が大きくなると対応量も膨らみ、本来の業務にしわ寄せがいくことも少なくありません。
その点、運用サポートがあるサービスでは「よく聞かれる新しい質問をFAQに追加」「回答精度を定期的に改善」「チャットの会話ログを分析して改善提案」などを専門スタッフが代行してくれることがあります。
こうしたサポートは単なる“おまけ”ではなく、チャットボットを継続的に成長させるために不可欠です。サポート体制が整っていれば、常にユーザーにとって役立つボットを維持でき、長期的な導入効果を最大化することにつながります。
分析・レポート機能はあるか
チャットボットの強みの一つは、ユーザーとのやり取りがすべてデータとして蓄積されることです。分析機能やレポート機能が備わっていれば、「どの質問が多いのか」「どの段階で離脱が発生しているのか」といった傾向を可視化でき、サイト改善や新しい商品開発のヒントにつながります。
たとえば「料金プランに関する質問が集中している」と分かれば、料金ページの表現を見直したり比較表を追加する、といった具体的な改善につなげられます。
逆に、分析やレポート機能が弱いサービスを選んでしまうと、せっかく蓄積されたデータを活かすことができません。その結果「導入したものの効果が見えない」「ユーザーの声を拾いきれない」という状況に陥る可能性もあります。
コストパフォーマンスに優れているか
最後に忘れてはならないのがコスト面です。高機能であっても、自社の利用シーンに合わなければ費用対効果は低くなってしまいます。
たとえばFAQ対応だけで十分なのに高額なAI型を導入すれば、投資に見合った効果は得られません。逆に、営業支援や商品推薦など幅広い機能を使う予定があるなら、多少費用がかかっても長期的に見て効率が上がるケースもあります。
導入時の価格だけでなく、運用のしやすさや成果を考えて判断することが大切です。
チャットボット導入で気をつけたいポイント
チャットボットは問い合わせ対応の効率化に役立つ一方で、万能ではありません。導入にあたっては、適切な運用を考慮しないと逆効果になることもあります。ここでは、導入時に注意すべきポイントを解説します。
完全な自動化は難しい
現在のチャットボットは、事前に設定されたルールや過去の学習データをもとに回答を行います。そのため、想定外の質問や複雑な内容には対応しきれず、有人対応が必要になる場面も多いのが実情です。
特に、カスタマーサポートをすべて自動化しようとすると、かえって対応品質が低下するリスクがあります。チャットボットの役割は、あくまで一次対応の効率化であり、難易度の高い問い合わせには適切に有人対応へ引き継ぐ設計が必要です。
複数の質問を同時に処理するのが苦手
チャットボットは基本的に、ユーザーからの質問を一つずつ処理する設計になっています。例えば、一度に複数の質問を投げかけられると、意図を正しく理解できず、適切な回答ができないケースがあります。
こうした課題を補うためには、「質問をひとつずつ入力してください」などの案内を入れる、もしくはチャットボットの限界を理解した上で、有人対応との連携を強化することが重要です。
チャットボット導入に向かないケースもある
すべての企業・サービスがチャットボットを導入すれば成功するわけではありません。問い合わせの性質によっては、チャットボットが適さないケースもあります。
例えば、以下のようなケースでは、チャットボットだけで対応しようとするとかえって不便を招くことがあります。
- 個別のヒアリングが必要な問い合わせ (オーダーメイドの相談、複雑な契約内容の説明など)
- ユーザーの感情に寄り添う必要がある対応 (クレーム対応、トラブル時のサポートなど)
このような分野では、チャットボットを無理に活用するのではなく、有人対応と適切に組み合わせることが重要です。導入前に、自社の問い合わせ内容を分析し、チャットボットの強みが活かせるかどうかを見極めることが求められます。
適切な運用でチャットボットの効果を最大化する
チャットボットは、適切な用途で活用すれば業務効率化や顧客対応の改善につながるツールです。しかし、すべての問い合わせを自動化できるわけではないため、導入前にその限界を理解し、有人対応とのバランスを取ることが成功の鍵となります。
導入を検討する際は、「チャットボットだけで対応できる範囲」と「有人対応が必要な範囲」を明確に分け、最適な運用フローを設計することが重要です。
クーシーが描くチャットボットの未来
いま、チャットボットは「よくある質問に答えるだけのツール」ではなく、
商品案内・予約受付・資料請求・採用対応など、あらゆるお客様対応を担う存在へと進化しています。
クーシーは、企業の想いやサービス内容をAIに学ばせ、
人のように自然に会話できるチャットボットをつくります。
それは、ユーザーの“迷い”や“ためらい”を拾い、
自然な会話で背中を押す、新しいパートナーのかたち。
クーシーは、こうした“人に寄り添うAI体験”を、
これからのWebのあたりまえとして育てていきます。
会話が生まれることで、CVRも満足度も上がる。
クーシーは、その第一歩を一緒に形にします。

この記事を書いた人
クーシーブログ編集部
1999年に設立したweb制作会社。「ラクスル」「SUUMO」「スタディサプリ」など様々なサービスの立ち上げを支援。10,000ページ以上の大規模サイトの制作・運用や、年間約600件以上のプロジェクトに従事。クーシーブログ編集部では、数々のプロジェクトを成功に導いたメンバーが、Web制作・Webサービスに関するノウハウやハウツーを発信中。
お問い合わせはこちらから
Web制作デザイン、丸ごとお任せ
お問い合わせする
執筆者:クーシーサイト編集部 デザイン:ピョータント
COOSYの
制作実績
UIUXと美しさを両立させた、クーシーが誇る成功事例一覧。
課題解決のアイデア満載です。