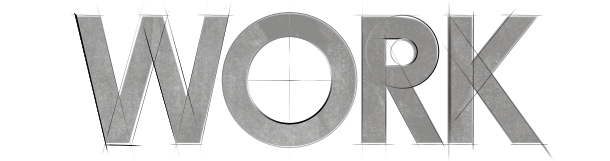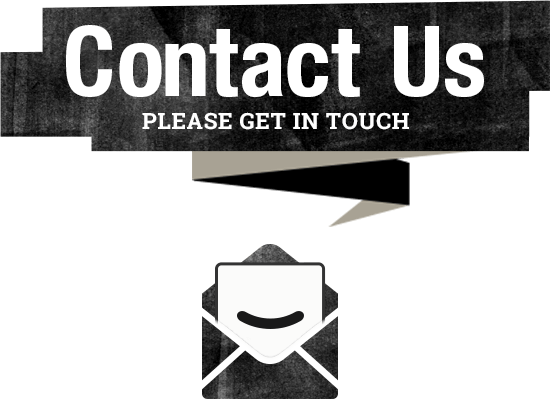大学公式サイト制作の“本質”とは? 多様なステークホルダーを導く情報設計とブランディングのポイント

「大学の魅力を、Webサイトでもっと伝えたい…」
「関係者が多く、各所からの要望をまとめるだけで一苦労だ」
「情報が多すぎて、サイト構造がまるで“倉庫”のようになってしまっている」
これらの課題は、大学という組織が持つ構造的な「難しさ」に起因するものです。私たちWeb制作会社クーシーも、プロジェクトの現場でその複雑さを日々痛感しています。
だからこそ本記事では、みなさんと共に「これからの大学公式サイトのWeb戦略」を考えたいと思います。その第一歩として、大学サイトならではのWeb制作・運用のポイントや成功事例を解説します。
なぜ大学「公式サイト」の制作は難しいのか?
では、なぜ大学サイトの制作はこれほど難しいのでしょうか。その難しさの正体は、主に3つの「壁」にあります。
1つ目の壁は、ステークホルダーの多様性という“壁”です。受験生、在学生、研究者、卒業生、企業…。目的もITリテラシーも全く違う人々を、同じ「公式サイト」で迎えなければなりません。この複雑な情報の整理こそ、担当者の頭を悩ませる点ではないでしょうか。
2つ目の壁は、コンテンツの膨大さと専門性という“壁”です。学部や入試情報はもちろん、最先端の研究成果といった高度に専門的な内容まで、扱う情報は質・量ともに膨大です。
3つ目の壁は、「伝統」と「革新」の両立という“壁”です。伝統に寄せれば硬派で近寄りがたく、革新や若者向けに寄りすぎれば軽薄に見えてしまうかもしれません。
これら“壁”を乗り越えるような、バランス感覚のある創造性こそ、大学サイト制作やブランディングの難しさでしょう。
優れた大学公式サイトが持つ3つの原則
では、これらの厄介な「壁」を乗り越え、成果を出している大学サイトは、一体何が違うのでしょうか。
それは、見た目のデザインや機能といった表面的な要素だけでなく、その根底に流れる共通の「原則」を大切にしている点です。ここでは、複雑なプロジェクトを進める上での判断の拠り所となる「3つの原則」をご紹介します。
原則1:多様性を束ねる「ブランド体験」
目的の異なる多様な訪問者に対応するためには、サイト全体で「一貫したブランド体験」を提供することが重要です。これは、単に「受験生向け」「在学生向け」と入り口を分けるだけでなく、どのページを訪れても、その大学“らしさ”が伝わる状態を目指す考え方です。
具体的には、ロゴやキーカラー、書体といったデザインのルールに加え、文章のトーン&マナー(ですます調、漢字とひらがなのバランスなど)も統一し、サイト全体で遵守します。これにより、どのページを見ても「〇〇大学らしさ」が感じられ、ユーザーに安心感と信頼感を与えます。
原則2:知の拠点としての権威性と社会貢献性の両立
大学サイトが発信するメッセージには、最先端の研究成果が示す「権威性」と、地域連携や公開講座などで示される「社会貢献性」という、2つの重要な側面があります。この2つを統合したストーリーで大学の価値を伝えることが重要です。
例えば、研究者や学問を紹介する際は、それらが「社会に向けたどのような有益な問いや課題解決につながるのか」という視点を加えます。
こうしたストーリーにより、研究シーズを探す企業や連携を模索する自治体にとって、大学の価値が具体的に理解しやすくなります。また、受験生や保護者に対しても、大学の社会的な意義が伝わり、教育機関としての信頼性が高まります。
原則3:膨大な情報を整理し届ける「戦略的な情報/UIUX設計」
数百ページを超えることも珍しくない大学サイトにおいて、その使いやすさは、見た目のデザイン以前の、土台となる情報設計の段階に大きく左右されます。
戦略的な設計とは、「誰が、どんな目的でサイトを訪れるか」というユーザー行動を第一に、情報配置やサイト構造を最適化していくアプローチです。サイトマップを作る際は、「受験生が入試情報に2クリックでたどり着けるか?」「スマホで閲覧した際に、重要な情報がすぐに見つかるか?」といった具体的な利用シーンを想定し、目的達成までの最短経路を設計することが求められます。
大学公式サイト制作で重要な9つのポイント
次に3つの原則という「考え方」を、実際のWeb制作・運用に落とし込むポイントを9つ解説します。ブランディングのような上流工程から、具体的な機能、そしてプロジェクトの進め方まで、幅広くご紹介します。
①大学の歴史と未来を語るブランディング戦略
大学のブランドは、歴史や建学の精神といった「過去からの資産」と、ビジョンや研究活動が示す「未来への約束」で成り立っています。これらをロゴやデザイン、コンテンツに一貫して反映させ、大学ならではの「らしさ」をWebサイト全体で表現することが全ての土台となります。
②ステークホルダー・ペルソナ設定の重要性
大学サイトは多様なステークホルダーに利用される分、誰を最優先ターゲットとするかについて関係者間の認識のすり合わせが不可欠です。ターゲットを絞るこの「選択と集中」の意思決定が、誰にも響かないサイトになることを防ぎ、プロジェクトの成果を大きく左右します。
③研究力と教育環境を伝えるコンテンツ戦略
大学の核となる「知」の魅力を、わかりやすく伝えるコンテンツ力もとても重要です。最先端の研究成果を社会課題と結びつけて解説したり、独自の教育プログラムの価値を在学生の声と共に紹介したりすることで、大学の提供価値を具体的に示すことができます。
④「環境」と「人」(教員・学生・卒業生)で魅せる
優れた施設や学習環境はもちろんですが、大学の魅力の源泉は「人」にあります。情熱的な教員、いきいきと学ぶ在学生、社会で活躍する卒業生。彼らのストーリーを通じて、大学のリアルな熱量やカルチャーを伝えることが、共感を呼ぶ最も効果的な手法です。
⑤グローバルな情報発信(多言語対応)
グローバル化が進む現代において、多言語対応も必須の要件です。単に日本語の情報を翻訳するだけでなく、留学生や海外の研究者が必要とする情報(入学要件、研究者情報など)を戦略的に整理し、わかりやすく提供することが求められます。
⑥動画を活用した魅力の最大化
キャンパスの美しい風景、活気あるイベントの様子、複雑な研究内容の解説など、テキストや写真だけでは伝えきれない「空気感」「熱量」「面白さ」を伝えるには動画が最適です。オープンキャンパスの疑似体験や、研究室のショートツアーなど、さまざまな有効な活用法があります。
⑦生成AI対応チャットボットや高度なサイト内検索機能の実装
膨大な情報の中からユーザーが必要な情報へスムーズに導く機能は、サイトの満足度を大きく左右します。特に近年はチャットボットの導入が増加しており 、国立大学で初となる東北大学の生成AI対応チャットボット導入は、24時間365日対応の新しい窓口サービスとして注目されています(詳細は下記記事後半にて)。
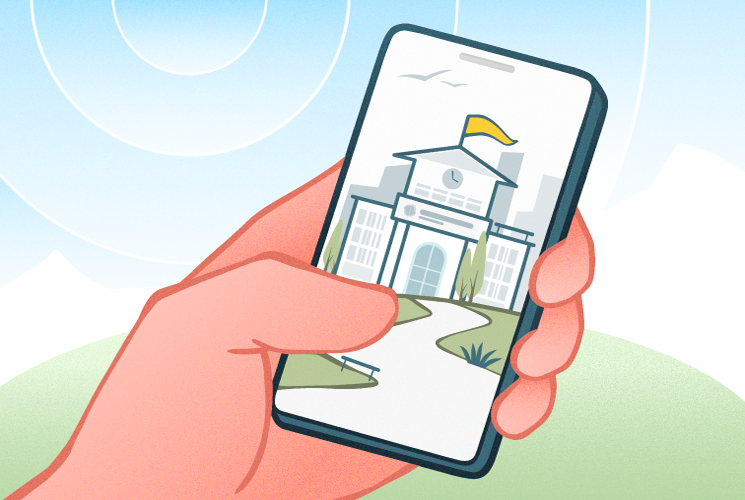
大学スマホサイトの使いやすさランキング最新版! AIチャットボットが示す新トレンドとは?
⑧公共機関としてのアクセシビリティ対応
年齢や障害の有無に関わらず、誰もが平等に情報を得られるよう配慮するWebアクセシビリティは、公共性の高い教育機関の責務です。毎年10月に公開される日経BPコンサルティングのユーザビリティ調査でも、文字の大きさや操作のしやすさといった項目が重要な評価指標となっています。
参考
⑨学内調整を円滑にするプロジェクトマネジメント
大学サイトのプロジェクトは、学内の多様な意見の合意形成が成功の鍵を握ります。上記の記事で紹介する東北大学の事例では、若手職員や有志の学生がDX推進チームとしてプロジェクトに参加する形が取られました。こうした立場の異なる有志の取り組みは、これからの大学における新しいプロジェクトの進め方としても参考になるのではないでしょうか。
【ポイント別】大学公式サイトの成功事例
では、これまで解説してきた原則やポイントが、実際の大学サイトでどのように活かされているのでしょうか。ここでは、特に優れた取り組みによって成果を上げている3つの大学を、それぞれの特徴とともにご紹介します。
【ブランディングの成功事例】千葉工業大学

参考
“ユニークでエッジの効いた工業大学”としてのブランドイメージを確立し、大きな成果を上げているのが千葉工業大学です。同学は、伊藤穰一氏の学長就任を機に、世界的なデザインスタジオ「Pentagram」と共にリブランディングに着手し、その一環としてWebサイトをリニューアルしました。
新たなサイトのトップページでは、大学の理念や抽象的なイメージではなく、実際の「研究」の魅力にフォーカスした動画が配置されています。最先端の研究成果や活動実績を前面に押し出すことで、同学が持つ先進性と社会的な価値を訪問者に直感的に訴求しています。また、学長自身の視点で大学の挑戦を発信する「学長だより」といったコンテンツも、大学の「変革の姿」を力強く印象づけています。
こうした戦略的なブランディングが功を奏し、2025年度入試では志願者数が全国1位となりました。大学ブランディング戦略を再構築し、その目指す姿をWebサイト上で明確に表現して、成果へとつながった好事例です。
【広報戦略の成功事例】近畿大学

参考
広報を起点とした巧みな話題づくりで、大学のブランドイメージを劇的に変革したのが近畿大学です。「固定化された大学の序列を広報の力で変える」という強い意志のもと、経営戦略本部長の世耕石弘氏が中心となり、数々の挑戦的な施策を打ち出してきました。
その象徴的な例が、日本の大学で初めて実施した「完全インターネット出願(近大エコ出願)」です。願書を撤廃するというニュース性の高い決断を、広告やプレスリリースを通じて大々的にPRし、大きな話題を創出。これらの「広報ファースト」の姿勢が、かつて一般入試の志願者数日本一を達成する大きな原動力となりました。
テレビニュースでも取り上げられた、つんく♂氏がプロデュースする「ド派手な入学式」も、単なるパフォーマンスではなく、「第一志望でなくても近大で頑張ろうと思ってもらいたい」という明確な目的を持った広報戦略に基づいたものです。Webサイトを単なる情報伝達の場ではなく、戦略的なPRの舞台として最大限に活用し、大学のブランド価値を向上させた先進事例と言えるでしょう。
【情報設計・ユーザビリティの成功事例】北海学園大学

参考
徹底したユーザー視点に基づき、国内トップクラスの使いやすさを実現しているのが北海学園大学の公式サイトです。日経BPコンサルティングの「大学スマホ・サイト ユーザビリティ調査」では常に上位にランクインし、過去には調査史上最高の総合スコアを記録した実績を持ちます。
大学自身も、サイトリニューアルの際に「アクセス数の約7割を占めるスマートフォンを中心」とした設計思想を掲げ、誰もが快適に利用できるサイトを目指していることを公表しています。その姿勢は、ユーザビリティ調査で評価された、スマホサイトからPCサイト表示へ切り替えるボタンの実装といった、ユーザーの細かなニーズに応える地道な改善の積み重ねにも表れています。
単にトレンドを追うのではなく、ユーザーが本当に使いやすいサイトとは何かをデータに基づき追求し続けること。その誠実な姿勢が、第三者機関からの高い評価、そして訪問者からの信頼につながっていることを教えてくれる事例です。
大学ブランドの信頼に直結するWeb制作・運用ならクーシーへ!
大学の公式サイトは、大学の理念やブランドを体現し、多様なステークホルダーと未来をつなぐ、極めて重要なコミュニケーションのハブです。その複雑なプロジェクトを成功に導くには、戦略的な視点と、それを形にする確かな技術が求められます。
私たちWeb制作会社クーシーは、見た目のおしゃれさはもちろん、ユーザーファーストで使いやすく心地いい情報・UIUX設計に徹底的にこだわっています。なぜなら、大学サイトのように複雑で情報量が多いWebサイトほど、その使いやすさがブランドの信頼に直結するからです。
これまで、大学をはじめ、さまざまな教育機関やサービスのサイト制作で培った知見を活かし、それぞれの課題に最適な解決策をご提案してきました。
「何から手をつければいいかわからない」
「学内の意見をどうまとめれば…」
Webサイトに関するお悩みは尽きないかと存じます。私たちクーシーでは、そうしたお悩みに対して、無料でご相談を承っております。Webサイトに関する小さな疑問や、リニューアルの具体的な進め方についてなど、どんなことでも構いません。
ぜひお気軽に、下記のフォームからお問い合わせください。 みなさまの大学が持つ素晴らしい価値を、Webサイトを通じて最大限に発揮するためのお手伝いができれば幸いです。
お問い合わせはこちらから
Web制作デザイン、丸ごとお任せ
お問い合わせする
テキスト:蒼山 デザイン:ピョータント
COOSYの
制作実績
UIUXと美しさを両立させた、クーシーが誇る成功事例一覧。
課題解決のアイデア満載です。