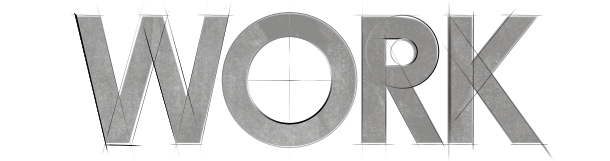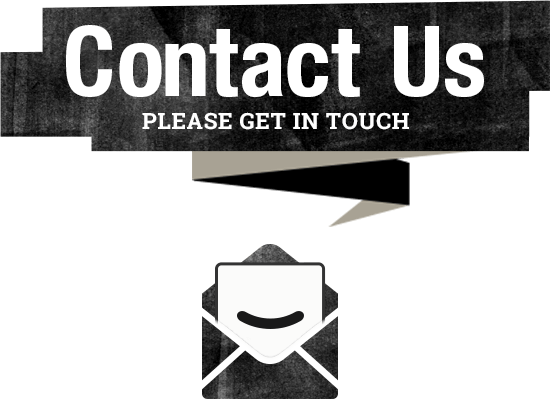【AI活用で提案書作成が楽になる!】今すぐ使える5つのテクニック

「提案書作成にまた時間を取られてしまった…」
「もっと効率的に、質の高い提案書を作れたらいいのに…」
日々の業務の中で、そう感じたことはありませんか? 提案書は、お客様や社内への価値提供の第一歩で、ビジネスの成否を左右することもあります。それほど重要にも関わらず、いえだからこそ、ビジネスパーソンの多くが提案書作成に要する時間について悩みを抱えています。
そんな切実な声に応えるべく、最新のAI技術を取り入れているWeb制作会社クーシーが、“今すぐ使える“生成AI活用テクニックを5つご紹介します!
また、方法だけではなく、おすすめの生成AIツールもピックアップしていますので、ぜひ最後までお読みください。
実務で提案書を作成するときの課題と悩み
具体的なテクニックに入っていく前に、なぜ「提案書作成」に時間がかかってしまうのか、「あるある」を踏まえて整理していきます。
「また資料作成か…」溜め息の理由
研修講師でもある筆者は研修でお会いする多くの方から、「提案書作成が得意で好き!」という声を聞くことは、残念ながら稀です。「また資料作成か…」と、つい溜め息が出てしまうものです。その気持ちは痛いほどよく分かります。
それは、提案書作成は決して正解のないものであり、精神的プレッシャーや煩雑さが伴うものだからだと思っております。
-
時間的制約:
タイトな納期の中で、質の高いアウトプットを求められる。
-
精神的負担:
相手に「刺さる」内容を自ら考え、正解のない問いを考え続けなければならない。
-
情報収集の手間:
そもそも必要なデータや事例を探し出すのに時間がかかる。
-
デザイン調整:
見栄えを整える作業に、意外と時間を取られる。
-
関係者調整:
上司や関連部署とのレビュー・修正の往復。
これらが複合的に絡み合い、提案書作成は「時間も気もつかう、大変な作業」というイメージが定着してしまっているのではないでしょうか。
なぜ提案書作成に時間がかかるのか?
提案書作成に時間がかかる理由は、単に「手を動かす時間」だけではありません。
本質的には、以下の要素がボトルネックとなっているケースが多くあります。
-
目的・ゴールの不明瞭さ:
「誰に」「何を伝え」「どうなってほしいのか」が不明確なまま作業を始めてしまう。
-
論点・構成の迷走:
伝えたいことが整理できず、話があちこちに飛んでしまう。
-
情報収集の非効率:
必要な情報がどこにあるか分からなかったり、情報の取捨選択に迷ったりする。
-
資料化への過剰な注力:
中身が固まる前に、デザインや言い回しにこだわりすぎてしまう。
-
手戻りの多さ:
上記の結果、レビューで大幅な修正が入り、やり直しが発生する。
これらの課題は、生成AIが登場する以前から存在していました。しかし、生成AIを効果的に活用することで、これらのボトルネックを解消し、プロセス全体を効率化できる可能性が出てきたのです。
提案書1件あたりに費やす時間の実態
「実際、提案書を1件作るのに、どれくらい時間がかかっているんだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。提案書の規模や内容、企業の文化によって大きく異なりますが、一般的な規模の営業資料でも数時間単位の時間を費やすといわれています。これが枚数の多いプレゼン資料になると比例してかかる時間も増えていくわけです。
例えば、HubSpot社の調査によると、セールス担当者の多くが資料作成などの間接業務に多くの時間を割いており、本来注力すべき顧客対応に十分な時間を確保できていないという実態が明らかになっています。
これはあくまで一例ですが、多くの企業で提案書作成が相当な時間的コストになっていることは間違いないでしょう。1件あたり数時間かかっているとして、月に何件も作成するとなれば、その負担は計り知れません…。
出典
よくある勘違い:「資料をきれいに作ること」=ゴール
ここで、提案書作成における非常に重要な、しかし見落とされがちな「勘違い」について触れておきたいと思います。それは、「資料をきれいに作ること」自体がゴールになってしまっているケースです。
もちろん、分かりやすく、見栄えの良い資料は重要です。しかし、提案書の本来の目的は、「相手に価値を伝え、期待するアクション(契約、合意形成など)を引き出すこと」のはずです。資料はあくまでそのための「手段」に過ぎません。
この「目的」と「手段」を混同してしまうと、「とにかく見栄えの良いスライドをたくさん作らなきゃ」「アニメーションを凝ってみよう」といった、本質的ではない部分に時間と労力を浪費してしまうことになります。
前述の「資料をきれいに作ること=ゴール」という勘違いは、特に生成AIの登場によって、より陥りやすい罠になった側面もあります。
生成AI資料作成のリアルな壁
「生成AIに頼めば、それっぽい提案書を自動で作ってくれるはず」
そんな期待を持つ方も多いでしょう。
しかし、実際には“即戦力”となる洗練された資料を生成AIのみで生み出すことは難しいのが実情です。
なぜ、現時点で生成AIへ丸投げすることが難しいのか、現状の生成AIは、以下のような課題を抱えています。
-
文脈把握の難しさ:
会社の強み、提案先の状況、業界特有のニュアンスなどを完全に理解して、最適な提案を自動生成することは難しい。
-
情報の正確性:
参照するデータが古かったり、誤った情報を生成したりする(ハルシネーション)可能性がある。ファクトチェックは必須。
-
独自性・具体性の欠如:
一般的・抽象的な表現になりがちで、相手に「自分たちのための提案だ」と感じさせる具体性や熱意を込めるのは難しい。
-
デザインの単調さ:
AIによる自動デザインは便利だが、企業のブランドイメージや伝えたい内容に完全に合致するとは限らない。テンプレート的になりがち。
研修参加者からも、「AIが出力した文章をそのまま使えず、結局自分で大幅に書き直した」「期待した構成やデザインにならなかった」といった声はよく聞きます。
生成AI時代の効率的な提案資料作成とは
さぁ、ここまで、よくある悩みと生成AI丸投げでの資料作成での限界を語ってきました。
では、どうすればAIを効果的に活用し、質の高い提案書を効率的に作成できるのでしょうか?
その答えは…
「提案書作成をタスク単位で細分化し、AIに得意領域を任せる」
というアプローチです。
ここからAIを活用した提案書作成のテクニックを紹介していきますが、最初に肝となるのが提案書作成の本質的なステップを理解することです。
提案書作成は5つの明確なステップで構成されているのです。
提案書作成の5ステップ
-
ゴール設定:
誰に、何を伝え、どうなってほしいのか? 提案の目的と着地点を明確にする。
-
論点設定:
ゴール達成のために、何を、どの順番で伝えるべきか? 提案の骨子(ストーリー)を設計
-
情報収集:
設定した論点を裏付けるデータ、事例、根拠などを集める。
-
構造化:
集めた情報を論点に沿って整理し、分かりやすい流れに組み立てる。
-
資料化:
構造化された内容を、具体的な文章や図解、デザインに落とし込む。
この流れを意識せずに、いきなり「資料化」から入ってしまうと、手戻りが増え、時間ばかりがかかる結果になりがちです。
上記の5つのステップにおいて、どこを人間が担い、どこでAIの力を借りるのか。この見極めこそが、AI活用による提案書作成効率化の鍵となるのです。
人間が主導すべき領域
-
ゴール設定:
提案の最終目的、戦略的な判断。
-
論点設定(骨子):
提案全体のストーリー設計、独自の価値提案。
-
最終的な判断・調整:
AIの出力内容の評価、ファクトチェック、顧客との関係性やニュアンスを踏まえた表現調整、最終的な意思決定。
AIの活用が効果的な領域
-
情報収集:
広範な情報の検索、関連情報のリストアップ、長文資料の要約。
-
構造化(たたき台作成):
論点に基づいた構成案の生成、セクションごとのアイデア出し。
-
資料化(ドラフト作成・効率化):
各セクションの文章案作成、表現の言い換え、図解アイデアの提案、定型的なスライドデザインの補助。
-
壁打ち・アイデア出し:
新しい切り口や表現のヒントを得るための対話相手。
つまり、戦略的・創造的な思考や最終判断は人間が担い、情報収集や定型的な作業、アイデアの幅出しといった部分でAIをアシスタントとして活用する。これが、現状における最も現実的で効果的なAIとの付き合い方だと、筆者は考えています。
現場で使える! AI活用資料作成テクニック5選
ここからは、具体的なAI活用テクニックを5つご紹介します。
① 壁打ち相手としてのAI活用

提案内容に行き詰まった時、新しい切り口が欲しい時、AIは優秀な「壁打ち」相手になります。
活用例
「〇〇業界の△△という課題に対し、弊社の□□(サービス・製品)を活用した提案の切り口を5つ考えてください」
「この提案コンセプトについて、想定される反論や懸念点を挙げてください」
「提案のタイトル案を10個、キャッチーなものと信頼性を重視したもので作成してください」
ポイント
- 具体的な状況や制約条件を伝えることで、より的確な回答を引き出せます。
- AIの回答を鵜呑みにせず、「発想のヒント」として活用しましょう。人間だけでは思いつかなかった視点が得られることがあります。
② 論点整理・構成案の高速作成
提案の骨子となる構成案(目次)のたたき台作成は、AIが得意とするところです。
活用例
「〇〇(提案先)向けの□□(提案内容)に関する提案書の構成案を作成してください。目的は△△です。含めるべき要素は[課題、解決策、導入効果、実績、費用、スケジュール]です」
「以下のキーワードを含む提案書の目次を作成してください:[キーワード1、 キーワード2、 ...]」
ポイント
- 提案の目的、ターゲット、含めたい要素を明確に指示することが重要です。
- 生成された構成案をベースに、人間が戦略的な視点で取捨選択・修正を加えることで、質の高い構成を短時間で作成できます。
③ 情報収集・要約
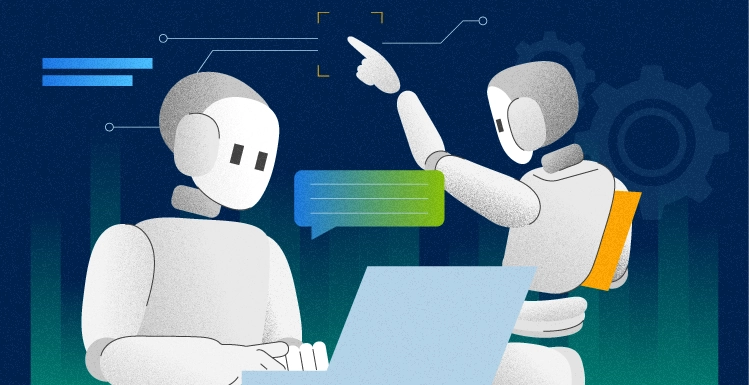
提案に必要なデータや事例、競合情報などを集める作業は時間がかかります。AIは、この情報収集と要約を大幅に効率化してくれます。
活用例
「〇〇市場の最新動向に関する信頼できる情報源をいくつか教えてください」
「以下のURLの記事を300字で要約してください」
「弊社のサービスと競合の△△サービスを比較し、機能面での主な違いをリストアップしてください」
(※最新かつ正確な情報は別途確認が必要)
ポイント
- 情報の正確性には注意が必要です。特に統計データや競合情報は、必ず一次情報や信頼できる情報源でファクトチェックを行いましょう。
- 長文のレポートや記事の要点を素早く掴むのに非常に役立ちます。
④ 各セクションのドラフト作成
構成が決まったら、各セクションの文章を作成するフェーズです。ここでもAIは、文章の「たたき台」作成に貢献します。
活用例
「提案書の『導入効果』セクションを作成します。以下の効果[効果1, 効果2, 効果3]について、それぞれ具体的なメリットが伝わるように記述してください。ターゲットは〇〇企業の担当者です」
「自社サービス□□の特長を3つのポイントにまとめて、それぞれ解説する文章を作成してください」
ポイント
- AIが生成した文章は、あくまで「下書き」と捉えましょう。そのまま使えることは稀です。
- 自社の強み、顧客の状況に合わせた具体的な表現、熱意のこもった言葉などを人間が加筆・修正することで、説得力のある文章に仕上げます。
- 箇条書きでポイントを指示するなど、AIが理解しやすい形で依頼するのがコツです。
⑤ 表現の洗練・校正サポート
作成した文章を、より分かりやすく、説得力のあるものに磨き上げる作業や、誤字脱字のチェックにもAIは役立ちます。
活用例
「以下の文章を、より簡潔で分かりやすい表現に書き換えてください。」
「この文章を、より丁寧なビジネス表現に修正してください。」
「以下の文章に誤字脱字や文法的な誤りがないかチェックしてください。」
ポイント
- 複数の表現案を出してもらい、最適なものを選ぶことができます。
- 専門用語の解説を加えたり、比喩表現を使ったりといった指示も可能です。
- 校正機能は便利ですが、最終的なチェックは人間の目で行うことが重要です。(特に固有名詞や専門用語)
これらのテクニックを組み合わせることで、提案書作成の各プロセスを効率化し、人間はより創造的で戦略的な部分に集中できるようになります。
おすすめの資料作成支援AIツール3選
最後に、これらのテクニックを実践する上で役立つ、具体的なAIツールを3つご紹介します。それぞれ特徴が異なるため、目的に合わせて使い分けるのがおすすめです。
(1) ChatGPT:対話型AIの王道
OpenAI社が開発した、言わずと知れた対話型AI。文章生成、要約、アイデア出し、翻訳、コード生成など、非常に幅広いタスクに対応可能です。
提案書作成での活用
上記テクニック①~⑤のほぼ全てに対応できます。特に、壁打ち、構成案作成、ドラフト作成、表現の洗練において強力なアシスタントになります。無料プランでも十分に活用できますが、有料プラン(ChatGPT Plusなど)では、より高性能なモデルやプラグイン、データ分析機能などが利用可能です。
ポイント
プロンプト(指示文)の質が回答の質を左右します。具体的かつ明確な指示を心がけましょう。
(2) Claude:収集した情報を自然な日本語へ変換
Anthropic社が開発した対話型AI。自然で倫理的な回答を生成する傾向があるとも言われています。
提案書作成での活用
テクニック③(情報収集・要約)で特に力を発揮します。長いレポートや複数の資料を読み込ませて、提案資料に記載できる、自然で読みやすい文体に整える用途に適しています。
ポイント
日本語の処理能力も高いと評価されています。一度に扱えるテキスト量が多い(コンテキストウィンドウが大きい)のが特徴です。
(3)「Gamma」 や 「イルシル」:プレゼン資料作成特化型
テキストを入力するだけで、AIがプレゼンテーション資料(スライド)のデザインや構成を自動生成してくれるツールです。「Gamma」や「イルシル」などが代表的です。
提案書作成での活用
テクニック② (構成案の高速作成)の効率化に貢献します。特にデザインに時間をかけたくない場合や、たたき台となるスライドを素早く作りたい場合に有効です。AIが提案する構成やビジュアルをベースに、内容を編集していくことができます。
ポイント
デザインのテンプレートは豊富ですが、完全にオリジナルのデザインや細かい調整には限界がある場合も。まずは構成案やラフなデザイン案を短時間で作るツールとして捉えると良いでしょう。多くのツールで無料プランが提供されています。
これらのツールは日々進化しています。ぜひ実際に試してみて、ご自身の業務スタイルに合ったものを見つけてみてください。
AIを賢く使って、提案の本質に向き合う
今回は、AIを活用して提案書作成を効率化するための考え方と、具体的なテクニック、そしておすすめのツールをご紹介しました。
提案書作成は、時間も労力もかかる大変な作業です。しかし、AIを「目的達成のための手段」「優秀なアシスタント」として賢く活用すれば、その負担を大幅に軽減し、より質の高い提案を生み出す時間を確保できます。
そして重要なのは、AIに丸投げするのではなく、「ゴール設定」「論点設定」といった戦略的な部分は人間がしっかりと担い、情報収集やドラフト作成、表現の洗練といった部分でAIの力を借りるという役割分担を意識することです。
ご紹介したテクニックが、みなさまの提案書作成プロセスを少しでも改善し、お客様への価値提供という本来の目的に、より多くの時間とエネルギーを注げるようになる一助となれば幸いです。
生成AIとの上手な付き合い方を学び、日々の業務をより創造的で価値あるものにしていきましょう。
私たちクーシーは、引き続き最新AI技術を取り入れたクリエイティブを発信していきます。伴い、2025年4月よりAI検索で「表示される・選ばれる」ためのAI最適化を行う新サービス「AIO/LLMO診断サービス」も開始いたしました。デジタル領域のあらゆる課題解決は私たちにぜひお任せください。Webサイト制作を始め、各種サービスのお問い合わせは下記フォームより承ります。

この記事を書いた人
渡部 壮(わたなべ そう)
基幹ブランドの販売戦略立案や営業支援等の営業職経験後、現在は人材教育業界にて、Microsoft 365および生成AI領域に特化したセールス兼コンサルタントとして活動中。M365活用や生成AI利活用の支援を行うほか、研修講師としても登壇。機能紹介にとどまらず、現場目線での実務特化型の活用提案が強み。
お問い合わせはこちらから
Web制作デザイン、丸ごとお任せ
お問い合わせする
テキスト:渡部 壮 デザイン:カント
COOSYの
制作実績
UIUXと美しさを両立させた、クーシーが誇る成功事例一覧。
課題解決のアイデア満載です。