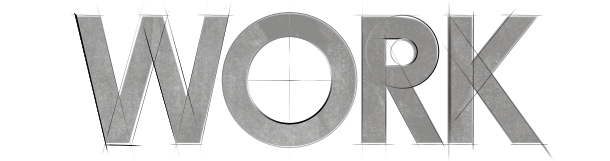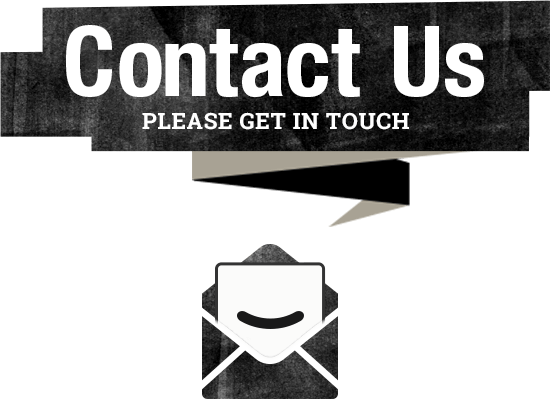コーポレートブランディングとは? 企業の「らしさ」を価値に変える戦略設計ガイド【成功事例付】
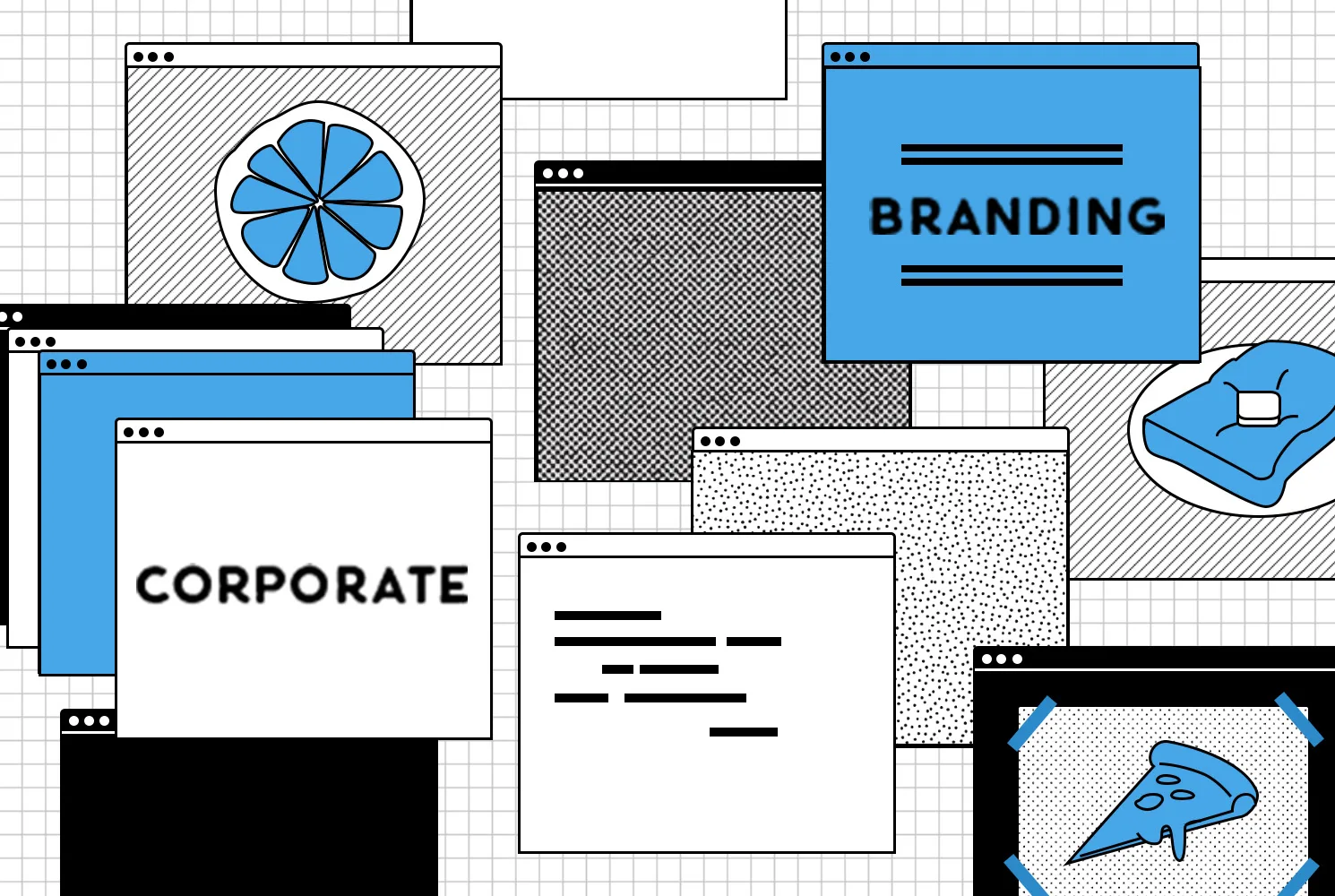
「コーポレートブランディング」と聞くと、多くの人が「おしゃれなロゴ」や「きれいなWebサイト」を思い浮かべるかもしれません。しかし、それはブランディングのほんの一部に過ぎません。
その本質は、企業の“あり方”そのものを定義し、顧客、従業員、社会といったあらゆるステークホルダーとの関係性を豊かにしていく、経営戦略そのものです。
本記事では、なぜ今コーポレートブランディングが重要なのかという時代背景から、具体的な進め方、そして成功企業の事例まで、その全体像を網羅的に解説します。Web制作会社として、数々の企業の「目に見えない想い」を「目に見えるカタチ」にしてきた私たちクーシーが、そのポイントを余すところなくお伝えします。
コーポレートブランディングが重視される背景とは?
なぜ今、多くの企業がコーポレートブランディングに取り組むのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く社会からの要請と事業環境の激変という、無視できない2つの大きな変化があります。
①社会からの要請:パーパス経営へのシフト
第一に、社会が企業を見る尺度が大きく変わりました。
かつての利益至上主義から、SDGsやESG投資といった世界的な潮流を背景に、社会貢献意識の高まりと同時に、「社会において、なぜその企業が存在するのか(Purpose)」という存在意義そのものが問われるようになったのです。
現代の消費者や投資家は、企業の“志”をしっかり見ています。この社会的な要請に応え、自社の存在価値を明確に打ち出すことは、現代ブランディングの重要なポイントです。
②事業環境の変化:VUCAの時代
第二に、企業が生き抜くためのルールそのものが変わっています。
未来予測が困難なVUCAの時代には、数年先の事業計画や目標はすぐに陳腐化しかねません。だからこそ、変化に対応しつつも揺るがない、企業の軸=ブランドが重要になります。
コーポレートブランディングとは? 多様なブランディングとの関係性
背景の次に、ブランディングの基礎知識を簡単に解説します。
コーポレートブランディングの周りには、インナーブランディングや採用ブランディングなど、関連する用語が数多く存在します。それらの関係性を整理し、コーポレートブランディングが何を指すのかをまず明確にしていきます。
企業の“あり方”そのものを定義する活動
コーポレートブランディングとは、あらゆる企業活動を通じて、企業そのもののブランドを構築し、その価値を高めていく戦略的な取り組みです 。
その目的は、企業の持つ独自性を一貫してユーザーに届け、信頼と共感を育み、特別な存在として認知されることです。言い換えれば、ロゴやデザインといった表面的なイメージ戦略に留まらず、企業の理念やパーパスといった“あり方”そのものを定義し、すべての活動に反映させることが、コーポレートブランディングの核心です。
アウター/インナーブランディングとの関係
コーポレートブランディングは、その対象によってアウターブランディングとインナーブランディングという2つの側面に分けられます。
-
アウターブランディング(社外向け)
顧客、取引先、株主、社会といった、企業の「外側」のステークホルダーに向けた活動。主な目的は、認知度の向上や良好な企業イメージの構築、商品・サービスの販売促進など。
-
インナーブランディング(社内向け)
従業員という、企業の「内側」に向けた活動。主な目的は、社内へのブランド浸透を通じて組織を活性化させ、従業員のエンゲージメントや働きがいを高めること。
この2つは車の両輪です。インナーブランディングによって従業員の士気が高まれば、商品やサービスの質が向上し、アウターブランディングの成功につながりやすくなります。逆に、社会からの評価が高まれば、従業員の誇りも育まれます。
コーポレートブランディングとは、この両面を統合的に進める活動だと言えるでしょう。
採用・商品ブランディングとの相乗効果
一方で、「採用」や「商品」といった特定の目的に特化したブランディング活動もあります。
-
商品・サービスブランディング
個別の商品やサービスに焦点を当て、その魅力を伝え、顧客による指名買いを促す活動。
-
採用ブランディング
採用候補者に向け、働く場所としての企業の魅力を伝え、入社後のミスマッチを減らし、質の高い人材を獲得するための活動。
コーポレートブランディングは、これらの個別ブランディングを支える土台です。
例えば、「環境に配慮した革新的な企業」というコーポレートブランドがあれば、そのイメージを追い風に商品を販促する一貫したマーケティング戦略が企画・実行できます。同様に、企業の“あり方”に共感した優秀な人材が集まりやすくなるなど、ブランディングに成功すれば、大きな相乗効果が生み出せます。
なお、戦略的な採用サイト制作で進める採用ブランディングについては下記記事で詳しく解説しています。

採用ブランディングは採用サイトを起点に「育てる」! 未来の採用活動をデザインする秘訣
コーポレートブランディングの目的と2つの本質的効果
次に、企業が抱えがちな課題を整理し、その上でブランディングがもたらす本質的な効果を2つに集約して解説しましょう。
ブランディングで解決できる事業課題チェックリスト
コーポレートブランディングが求められる背景には、企業が抱える様々な事業課題があります。ここでは、それらの課題を「社外(アウター)」「社内(インナー)」「経営・事業」の3つの視点からリストアップしました。ぜひチェックしてみてください。
アウターブランディングに関わる課題例
認知・理解不足
イメージの陳腐化・固定化
差別化の困難
ブランド価値の低下
ステークホルダーとの関係構築
インナーブランディングに関わる課題例
理念の形骸化・浸透不足
エンゲージメント・一体感の欠如
採用力の低下とミスマッチ
経営・事業構造の変化に関する課題例
事業ポートフォリオの変化
グローバル化への対応
事業承継と世代交代
サステナビリティ経営への要請
コーポレートブランディングがもたらす2つの絶大な効果
先ほどのチェックリストで挙げたような多岐にわたる課題に対し、コーポレートブランディングは大きく分けて2つの効果でその解決に貢献します。
効果1:シンボル化と差別化による「優位性」の確立
これは、企業の社外に対する影響力を生み出す効果です。というのも、別記事「Webブランディング入門ガイド」で解説しているように、ブランディングの基本は、デザインをおしゃれに洗練させることではなく、ターゲットの情緒に働きかけ、記憶し、好んでもらうことにあります。
つまり、数多くの競合の中から、顧客、求職者、投資家といったあらゆるステークホルダーに「その他大勢」ではなく「この会社でなくてはならない」と選ばれる明確な理由を作る。
その結果、特定のニーズにおいて真っ先に思い出してもらえる「第一想起」を獲得したり、顧客が比較検討せずに積極的に自社を選んでくれる「指名買い」を促進したりすることができます。これがブランディング効果の核心です。
効果2:理念共有による「組織力と求心力」の強化
続いては、企業の社内に対する結束力を高める効果です。
「私たちは何のために存在するのか」という企業の“志”が従業員一人ひとりに浸透することで、組織全体が同じ方向を向き、自律的に動く強いチームへと変わります。
従業員が自社に誇りを持ち、働きがいを感じられるようになることで、エンゲージメントが向上し、組織が活性化します。結果として、優秀な人材の定着や、採用におけるミスマッチの減少も期待できるでしょう。個の力を束ね、組織全体のパフォーマンスを最大化させる戦略的な仕組みがブランディング施策です。
コーポレートブランディングを始めるべきタイミングとは?
では次に、いつ・どのように進めていくべきかという具体的なポイントについてご紹介しましょう。コーポレートブランディングは、ステークホルダーとのあらゆるコミュニケーションに関わるため、理想を言えば「いつでも」取り組みたい施策です。
ですが、特に着手・見直しを検討すべき節目があります。ここでは、企業の成長ステージごとに、代表的な3つのタイミングをご紹介しましょう。
-
タイミング1:創業期・スタートアップ期
会社の第一印象と土台を作る最も重要な時期です。最初に企業の存在意義(パーパス)や理念を明確にし、ブランドの軸を定めることで、その後のすべての活動に一貫性が生まれます。
-
タイミング2:事業の成長・拡大期
事業や従業員が増え、「昔と何かが違う…」と感じ始めたら、それは見直しのサインです。組織の拡大に伴い、創業時の想いが薄まったり、顧客に与えるブランドイメージが曖昧になったりすることは少なくありません。成長フェーズに自社のブランドを再定義することで、さらなる飛躍に向けた基盤を固めます。
-
タイミング3:経営の変革・転換期
会社のあり方が大きく変わる節目は、ブランディングの絶好の機会です。内外の不安を払拭し、「私たちはこう変わる」という未来への意志を明確に示す必要があります。(例:事業継承・経営陣の交代、M&Aによる組織再編、主力事業の転換、周年記念など)
なお、どのタイミングで着手するにせよ、コーポレートブランディングは一朝一夕に成果が出るものではありません。企業の理念や価値観が組織文化として深く根付き、社外のステークホルダーにまでその評価が浸透するには相応の時間がかかります。
短期的な成果を追い求めるのではなく、中長期的な視点を持って継続的に取り組むことが成功の鍵となります。
コーポレートブランディングの進め方
次に具体的な進め方を見ていきましょう。ここでは、ブランディングを成功に導くための基本的な4つのステップをご紹介します。これは、企業の目に見えない想いを、目に見える「カタチ」に変えていくための重要なプロセスです。
ステップ⓪推進体制の構築
本格的な調査や分析に着手する前に、まずはプロジェクトを牽引する推進体制を整えましょう。コーポレートブランディングは、経営企画や広報といった一部の部署だけで完結するものではなく、全社を挙げて取り組むからこそ効果を発揮する施策です。
経営の意思決定を担う役員はもちろん、ブランドのメッセージを社外に発信する広報・マーケティング部門、社内に浸透させる人事部門、そして顧客と直接向き合う営業やサービス開発部門など、部署を横断したメンバーでチームを編成することが理想です。
ステップ①現状と市場の調査
まず最初に行うのは、自社の「現在地」を正確に把握することです。
-
自社分析
経営理念や、自社の強み・弱みを洗い出します。
-
ユーザー調査
顧客が自社にどのようなイメージを持っているかを調べます。
-
競合調査
競合他社と比較し、市場における自社の立ち位置を明らかにします。
この調査を通じて、自社が本当に価値を提供できる顧客グループ(セグメント)は誰なのか、市場機会はどこにあるのかを見極めていきます。詳細な調査のポイントは、別記事「STP分析のやり方を3ステップで解説」にまとめていますのでぜひ参考にご覧ください。
ステップ②コアな「らしさ」の策定
次に紹介するのが、「企業らしさ」を見える「カタチ」にする3つのステップです。
-
可視化:ブランド価値の関係整理
まずは、企業のブランド要素をブレインストーミングしながら付箋などで洗い出していきましょう。例えば、リストアップしたものをグルーピングし、最も重視する「コアバリュー」に沿って序列化すると、目に見えにくいブランド価値の関係性を視覚的に整理することができます。
-
言語化:MVV・PVなど経営理念の明示
定めたポジションを、誰が見ても分かる具体的な言葉やスローガンに落とし込みます。その最たるものが、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やPV(パーパス・バリュー)と呼ばれる経営理念や会社方針を言語化したものです。
-
シンボル化:イメージ連想の促進
言語化された理念を、ロゴ、キーカラー、デザインといった視覚的なシンボルに落とし込みます。ポイントは、それらシンボルから情緒的にイメージ(例えば、コーポレートサイトなら「信頼性」)してもらえるように戦略的なデザインを仕上げることです。
「らしさ」を定めることはもちろん、それがステークホルダーにどのように「響く」のか、自社のシーズと顧客ニーズのマッチングを考慮しながら検討を進めていきましょう。
ステップ③働きがいの言語化と浸透(インナーブランディング)
ステップ②で定めた「らしさ」を、従業員という企業の「内側」に浸透させます。従業員一人ひとりがブランドの体現者であり、その働きがいや誇りが、提供するサービスの質を大きく左右するからです。ブランドブックの作成や社内ワークショップなどを通じて、企業の“志”への共感を育み、組織の一体感を高めます。
ステップ④一貫したコミュニケーション戦略の設計と実行(アウターブランディング)
同時に、企業の「外側」に向けて、一貫したコミュニケーションを展開します。
策定したブランドアイデンティティに基づき、Webサイト、広告、SNSなど、あらゆる顧客接点(タッチポイント)で発信するメッセージやデザインのトーンを統一します。
特にWebサイトは、ブランドの世界観を伝え、ユーザーとの共感を育むための強力な「ハブ」となります。戦略を「体験」へと昇華させ、継続的に効果を測定・改善していくことが成功の鍵です。ブランディングにおけるコーポレートサイトの役割については、こちらの記事で詳しく解説しています。
コーポレートブランディングの成功事例
ここからは、コーポレートブランディングによって大きな成果を上げた国内企業の事例を2社ご紹介します。いずれも、本記事で解説してきた「パーパス経営へのシフト」「インナーとアウターの連動」「事業課題の解決」といったポイントを体現する、示唆に富んだ事例です。
事例1:パーパスは経営ツールである(ソニーグループ株式会社)
最初の事例は、日本を代表するグローバル企業、ソニーグループです。同社が掲げたパーパスは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」でした。
このパーパスは、CEO主導のもと、多様な事業体の社員たちを巻き込みながら策定されました。複雑化した組織において、社員一人ひとりが「自分たちは何のために存在するのか」という原点に立ち返り、自らの仕事と社会とのつながりを再認識する「組織力の強化(インナーブランディング)」を中心に進められた事例です。
具体的に行ったのが、イノベーションを生み出す土壌を育むために社員のアイデアを事業化するプログラムの整備や、パーパスに沿った行動を人事評価指標に加える仕組みの整備です。社内に浸透したパーパスは、誰もがゲームを楽しめるアクセシビリティ対応製品の開発など、具体的な事業活動にも反映されています。
結果、パーパスは従業員アンケートで9割近くが共感し、約8割が日々の仕事を通じて実践している/しようとしているという回答が集まったそうです。トップダウンで一方的なスローガンを通達するのではなく、社全体でパーパスを定義・浸透するプロセスそのものが、巨大で複雑な事業をまとめ上げ、推進する力の源であったのがわかる、ソニーの事例はまさにコーポレートブランディングの好例です。
事例2:「行動するブランド」が切り開いたBtoBビジネス(サイボウズ株式会社)
2つ目の事例は、グループウェア国内シェアNo.1を誇るサイボウズです。今でこそ「働きがいのある会社」として知られる同社ですが、そのブランドは、壮絶な「失敗」から始まりました。
2005年、急成長の陰でサイボウズの離職率は28%に達し、組織は崩壊の危機にありました。この危機的状況から脱却するために生まれたのが、現在の企業理念である「チームワークあふれる社会を創る。」です。
同社の特質すべき点は、この理念を掲げるだけでなく、人事制度の刷新といった「行動」で徹底的に体現した点です。その結果、離職率は28%から4%前後まで劇的に改善しました。
サイボウズの凄みは、この組織改革のプロセスを、社外へもオープンに発信し続けた点にあります。オウンドメディア「サイボウズ式」は、働き方の葛藤や組織の課題といった、自社のリアルを赤裸々に発信し、企業のきれいごとではないストーリーが共感を呼ぶメディアとなりました。
BtoB企業が自社の内情をここまでさらけ出すのは異例です。しかし、この「行動するブランド」としての姿勢が、働き方改革の先進企業という唯一無二のポジションを確立した要因でしょう。製品(kintoneなど)の売上増や、理念に共感した優秀な人材の獲得といった、強力な「優位性の確立(アウターブランディング)」につながったのです。
サイボウズの事例は、インナーブランディングの徹底こそが、BtoBビジネスにおける最強の差別化戦略となり得ることを教えてくれます。
「優位性の確立」と「組織力の強化」に向け、クーシーは伴走します。
本記事では、コーポレートブランディングの全体像を、その背景から具体的な実践ステップ、成功事例に至るまで解説してきました。
社会貢献意識の高まりと事業環境の激変(VUCAの時代)を背景に、その重要性は増すばかりです。その目的は、社外に対する「優位性の確立」と、社内に向けた「組織力の強化」に集約されます。
そして、その成功の鍵は、導き出したコアな「らしさ」を、一貫した「体験」としてすべての顧客接点で届け続けることにあります。
ソニーやサイボウズの事例が示すように、成功するブランディングは、常に企業の“あり方”そのものから始まります。それは、従業員の働きがいとなり、顧客に選ばれる理由となり、ひいては企業の持続的な成長を支える強力な経営資産となるのです。
ブランディングは壮大なプロジェクトに思えるかもしれませんが、その第一歩は、自社の「らしさ」とは何かをチームで話し合うことから始まります。
「自社の想いをどうカタチにすればいいか分からない」
「どこから手をつければいいか悩んでいる」
もしそうお考えでしたら、ぜひ一度私たちクーシーにご相談ください。また、ブランディングに寄与したさまざまなコーポレートサイト制作の実績はこちらでご覧ください。戦略の設計から、心を動かすWeb体験の実装まで、私たちはみなさまのビジネス成長に向け伴走します。
お問い合わせはこちらから
Web制作デザイン、丸ごとお任せ
お問い合わせする
テキスト:青山 俊之 デザイン:大坂間 琴美、佐野 由和
COOSYの
制作実績
UIUXと美しさを両立させた、クーシーが誇る成功事例一覧。
課題解決のアイデア満載です。