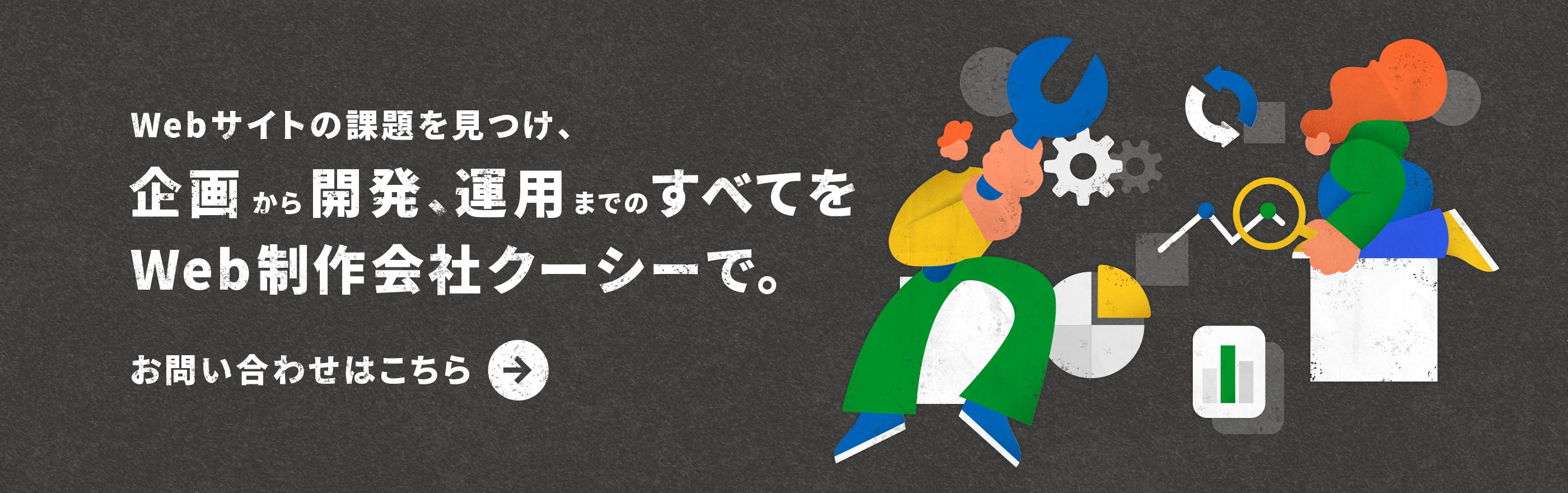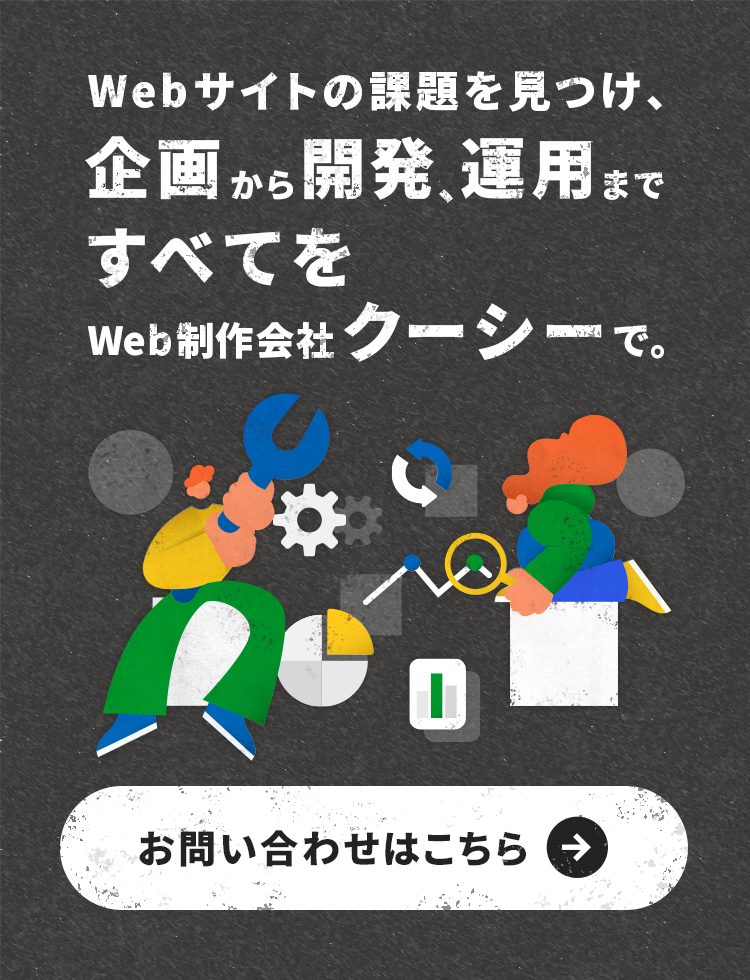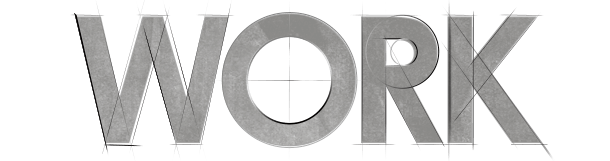未来を拓く大学ブランディング戦略とは? リーダーが動けば、学校が変わるわけ。

- 大学ブランディングとは?
- リーダーシップを必要とする大学ブランディングの背景
- 大学ブランディングの進め方:未来を創る5つのステップ
- 大学ブランディングの事例:成功の秘訣は戦略的な実行力と一貫性
- 成功要因の分析:レジリエントな大学ブランドを築く4つの柱
- 大学ブランディング戦略を成功に導くWebサイト実現ならクーシーへ!
18歳人口が減少し、「大学全入時代」が現実のものとなった今、大学は「選ばれる」ための努力が不可欠な時代を迎えています。本記事では、大学に独自の魅力と評判を生み出すための大学ブランディングについて、Web制作会社のクーシーが解説します。
大学ブランディングとは?
大学ブランディングとは、自学が持つ独自の価値(強みや教育理念)を明確に定義し、それを学生や保護者、教職員、地域社会といったあらゆるステークホルダーに伝え、共感を得ることで、「選ばれる」ためのポジションを築く経営戦略そのものです。
ブランディングとは、ロゴを刷新したり、おしゃれなパンフレットを作成したりすることではありません。あくまで、ターゲットユーザーの「選好」や「記憶」にはたらきかけるのがブランディングの基本です。
変化の激しい現代において、大学の価値を測るものさしとされてきた「偏差値」だけではなく、「その大学で何を学び、どんな未来を実現できるのか」という、一人ひとりの期待に応えることが求められています。何もしなければ淘汰されかねない厳しい時代だからこそ、自学の存在意義を社会に問い、未来の入学者との強固な関係を築くブランディングが、これまで以上に重要になってきています。
リーダーシップを必要とする大学ブランディングの背景
大学という組織は、学部や研究室、事務局など、多様なステークホルダーで構成されており、それぞれの歴史や文化、価値観を持っています。そのため、全学的な合意形成には時間がかかり、「改革」にアレルギー反応を示すケースも少なくないとよく言われます。
もちろん、学問の自由を基礎とする多様な価値観や熟慮も重要なのは前提としつつも、ブランディングは全学を挙げたメッセージを発信し、一貫した体験を提供しなければ成功し得ません。教員と職員の間でビジョンが共有されていなければ、発信するメッセージは多角的どころか、支離滅裂な印象を与えかねません。
だからこそ、学長や理事といった経営層や広報担当者が「この大学は、未来に向けてこう変わるんだ」という明確なビジョンを示し、強いリーダーシップで改革を牽引する必要があります。
大学ブランディングの進め方:未来を創る5つのステップ
では、具体的に大学ブランディングはどのように進めていけばよいのでしょうか。ここでは、未来の入学者に「選ばれる」大学になるためのプロセスを、5つのステップに分けて解説します。
Step 1. 現状分析:自校の「現在地」と「存在意義」を問い直す
ブランディングの第一歩は、自分たちの現在地を客観的に知ることから始まります。在学生や教職員へのアンケート、日経BPコンサルティングの「大学ブランド・イメージ調査」といった外部データ、SNS上での評判などを通して、世間から自学がどのように見られているのかを把握しましょう。
同時に、自学の歴史や建学の精神に立ち返り、「そもそも、我々の大学は社会においてどのような価値を提供するために存在するのか」というパーパス(存在意義)を問い直すことが重要です。このパーパスこそが、あらゆるブランディング活動の揺るぎない土台となります。
Step 2. ターゲット理解:未来志向の高校生のインサイトを掴む
次に、メインターゲットである高校生のインサイト(深層心理)を深く理解します。今の高校生は、単に「楽しそう」といった漠然としたイメージだけでは動きません。彼らは、社会課題への関心が高く、大学での学びが自らのキャリアや人生にどうつながるのか、常に「未来」を見据えています。
在学生へのインタビューや、高校の進路指導教諭へのヒアリングなどを通じて、「高校生は大学に何を期待しているのか」「どんな未来に不安や希望を抱いているのか」を徹底的に分析し、彼らの心に響くメッセージのヒントを探ります。
Step 3. ブランドコンセプト設計:独自の「提供価値」を定義する
現状分析とターゲット理解を踏まえ、自学が提供できる独自の価値、すなわち「バリュープロポジション」を定義します。「〇〇大学といえば△△」と、受験生や社会から第一に想起されるような、明確で魅力的なコンセプトを打ち立てましょう。
それは、特定の研究分野における圧倒的な実績かもしれませんし、手厚いキャリアサポート体制かもしれません。あるいは、独自の教育プログラムや、キャンパスが持つ唯一無二のカルチャーかもしれません。他大学には真似できない、自学ならではの「選ばれる理由」を磨き上げます。
Step 4. コミュニケーション設計:一貫したメッセージで「体験」を届ける
ブランドコンセプトが決まったら、それをあらゆるタッチポイントで一貫して伝えていくコミュニケーション戦略を設計します。Webサイト、SNS、動画、大学案内、オープンキャンパス、プレスリリースなど、受験生が触れるすべての媒体で、同じブランドイメージ、同じトーン&マナーで語りかけることが重要です。
例えば、「挑戦を後押しする大学」というコンセプトを掲げるなら、Webサイトでは卒業生の挑戦ストーリーを大々的に紹介し、オープンキャンパスでは学生が主体となる企画を実施するなど、コンセプトを「体験」として伝えられるような仕掛けを考えます。
Step 5. 効果測定と改善:PDCAサイクルを回し続ける
ブランディング効果を測ることは難しいものです。しかし、「闇雲な施策」や「実行して終わり」とならないように、施策の結果、ブランドイメージや認知度がどのように変化したのかをさまざまな指標から把握し、改善を繰り返すPDCAサイクルが不可欠です。
指標例には、オープンキャンパスの参加者数、大学名や学会名などの指名検索数、また志願者数や偏差値といった指標が挙げられます。他にも、「ブランド・イメージ調査」のスコア変動や、Webサイトのアクセス解析、アンケート調査などを通じて、「コンセプトはターゲットに届いているか」「施策は効果を上げているか」を多角的に検証します。地道な効果測定と改善の繰り返しが、ブランドを強く育てていくはずです。
大学ブランディングの事例:成功の秘訣は戦略的な実行力と一貫性
ここでは、優れたブランディング戦略によって、大学の価値を飛躍的に高めた大学の事例を4つ紹介します。それぞれ異なるタイプの「リーダーシップ」が、どのように変革の原動力となったかにご注目ください。
1. 近畿大学:常識を覆した「広報ファースト」戦略
「“入れ替え戦のないリーグ戦”と言われる、大学の固定化された現状を広報の力で変える」。この強い決意を持って近畿大学の改革を牽引したのが、現・経営戦略本部長の世耕石弘氏です。
同氏が率いる広報部門は、学内にあった「良い教育をすれば学生は集まる」という考えや、序列への諦めムードに対し、「広報ファースト」という明確な方針を掲げました。その象徴が、日本初の「完全インターネット出願」です。これを単なる業務改革ではなく、「一番乗り」の話題として戦略的にPR。批判を恐れず、古い願書を貼り付けた「願書請求しないでください」という広告で世間の度肝を抜き、その年の志願者数を2万人も増やすという劇的な成果を上げました。
世耕氏が語る「対外広報は最強のインナー広報だ」という言葉は、この戦略の本質を突いています。新聞やテレビで自学の先進的な取り組みが報道されることで、教職員や学生の意識が変わり、大学全体が「改革」を志向する好循環が生まれたのです。専門部門が強いリーダーシップと覚悟を持つことで、大学全体の文化をも変革できることを証明した、まさに王道の事例です。
2. 千葉工業大学:トップが牽引する未来へのビジョン
学長というトップリーダー自身が、大学のブランドを象徴し、未来へのビジョンを力強く牽引する。その最先端の事例が、伊藤穰一氏が学長を務める千葉工業大学です。
伊藤氏の学長就任を機に、大学は世界的なデザインファーム「Pentagram」と連携し、抜本的なリブランディングに着手。これは、ただのイメージチェンジではありません。「世界文化に技術で貢献する」という理念のもと、日本の大学を世界基準のステージに引き上げるという、伊藤氏の明確な意思決定の表れです。リニューアルされたWebサイトでは、抽象的な言葉ではなく、ロボットやAIといった具体的な研究成果のビジュアルが躍動し、大学の先進性を直感的に伝えています。
この事例が示すのは、トップリーダーが明確なビジョンを持ち、それを世界レベルのクリエイティブに落とし込むことで、偏差値とは異なる「未来への貢献」という新しい価値基準を社会に提示できるということです。「リーダーが動けば、大学が変わる」を最もダイナミックに体現したケースと言えるでしょう。
3. 東洋大学:コンセプトで未来を拓く「学際連携」
次にご紹介する東洋大学の事例は、学部新設において「何を学ぶか」以上に、「どのように学び、どう価値を創造するか」というコンセプトがいかに重要かを教えてくれます。
2017年、東洋大学は情報連携学部、通称「INIAD(イニアド)」を開設しました。特筆すべきは、学部長にTRONの開発者として世界的に知られる坂村健氏を招聘したことです。
坂村学部長が掲げたのは、「文理融合」の一歩先を行く「学際連携」という考えでした。プログラミングやデザイン、ビジネス、社会システムといった多様な領域を、学生が連携して横断的に学ぶ。このコンセプトを実現するため、1年次の全員寮生活や徹底したグループワーク、最先端のICT環境の整備など、ハード・ソフト両面に大胆な投資を実行しました。
その結果、INIADはIT業界を中心に高い評価を獲得し、就職率も大学内でトップクラスを誇ります。「東洋大学といえばINIAD」という新たなブランドイメージを確立し、多くの受験生の支持を集めることに成功しました。
この事例は、学部新設によるブランディングを成功させるためには、教育の「思想」や「コンセプト」を深く掘り下げ、それを具現化する仕組みまでデザインしきることの重要性を示唆しています。
4. 信州大学:「地域との共生」が築く不動のブランド
地方の国立大学にとって、18歳人口の減少や大都市圏への学生流出は深刻な課題です。しかし、その逆境を独自の強みに転換し、ブランド価値を高めているのが信州大学です。その戦略の核は、「地域との共生」。言うは易しですが、信州大学は学長のリーダーシップのもと、スローガンに留まらない組織的なアクションでこれを実現しています。
象徴的な取り組みが、長野県庁内に大学の連携拠点(信州大学長野県連携室)を設置したことと、県内各地に点在する分散キャンパスのデメリットを逆手に取り、それぞれのキャンパスが立地する地域の産業や文化と深く連携する「地域密着型教育」を推進したことの2点です。県レベルの行政との連携も深めながら、大学全体が長野県という広大なフィールドを活かし、地域の課題解決に貢献する姿勢と体制を築き上げました。
こうした取り組みは、外部からの評価として結実します。一般社団法人大学イノベーション研究所が実施する「大学の地域貢献度調査」において、信州大学は2010年代後半から全国で総合1位や2位の最高評価を連続して獲得。こうした外部評価だけではなく、2023年度の入試では4年ぶりに志願者数が増加に転じるなど、着実な成果につながっています。
信州大学の事例は、自校が持つ立地や歴史といった独自の資産を、地域との共生という視点で見つめ直すことが、未来につながる大学ブランディング戦略であることを教えてくれます。
参考:
大学の地域貢献度調査 信大は全国2位にランクイン|信州大学
成功要因の分析:レジリエントな大学ブランドを築く4つの柱
ご紹介した4つの大学は、いずれも厳しい環境の中で見事にブランド価値を高めています。その成功の裏には、社会の変化に対応し、持続的に価値を高めていく「レジリエント(強靭)なブランド」を築くための共通した要点がありました。ここでは、それらを「4つの柱」として分析します。
柱1:ビジョンを言語化する「コンセプト」の力
成功している大学は、例外なく「私たちの大学は何を目指すのか」という明確なビジョンを持っています。そして、それを教職員から受験生まで、誰もが理解し、共感できる独自の「コンセプト」に明確にしています。
柱2:変革を牽引する「多様なリーダーシップ」
強いブランドは、強力なリーダーシップから生まれます。しかし、その形は1つではありません。千葉工業大学のような学長主導のトップダウンもあれば、近畿大学のように専門部門(広報部)がエンジンとなるケースもあります。また、東洋大学のように、外部から招聘したスターリーダーが組織を牽引することもあります。重要なのは、役職ではなく「誰が改革の旗を振り、一貫して施策として実行するのか」を明確にすることです。
柱3:偏差値に頼らない「独自の価値軸」の創造
今回ご紹介した大学は、その「偏差値」という序列から脱却し、自ら新しい「価値軸」を創り出し、社会に提示しています。実際、学生も従来の「偏差値」だけではなく、その大学で過ごす4年間の経験とその先に価値を見出しつつあると言われます。
柱4:ビジョンを具現化する「覚悟ある投資」
成功事例の背景には、必ずビジョンを具現化するための「覚悟ある投資」が存在します。 東洋大学のICT環境や寮への投資、千葉工業大学の世界的なデザインファームへの依頼など。これらは単なるコストではなく、大学の未来を創るための戦略的な投資です。大学のブランドとして見える「カタチ」にするためにヒト・モノ・カネを本気で投下できるか。その覚悟が、ブランドの行く末と信頼性を大きく左右します。
大学ブランディング戦略を成功に導くWebサイト実現ならクーシーへ!
今日の大学ブランディングは、リーダーが掲げたビジョンや独自の価値軸を、いかにステークホルダーに届け、共感を呼ぶかにかかっています。そして、その戦略の成否を分ける最も重要な接点が、大学の顔であり、情報発信基地となるWebサイトです。
私たちWeb制作会社クーシーは、見た目のおしゃれさはもちろん、大学独自の「コンセプト」や「価値軸」を、ユーザーが直感的に体験できるUIUX設計に徹底的にこだわります。なぜなら、Webサイトこそが、リーダーの描いた未来像を初めて体感する場であり、その体験の質がブランドへの信頼そのものになるからです。
これまで、大学をはじめ、さまざまな教育機関やサービスのサイト制作で培った知見を活かし、それぞれのブランド戦略に最適な解決策をご提案してきました。
「新しいブランドコンセプトを、Webでどう表現すればいい?」
「学内の様々な意見を、新しいWebサイトにどう集約すれば…」
ブランディング戦略とWebサイトに関するお悩みは尽きないかと存じます。私たちクーシーでは、そうしたお悩みに対して、無料でご相談を承っております。Webサイトに関する小さな疑問や、リニューアルの具体的な進め方についてなど、どんなことでも構いません。
ぜひお気軽に、下記のフォームからお問い合わせください。みなさまの大学が持つ、伝統と未来への情熱がこもったブランド価値を、Webサイトを通じて最大限に発揮するためのお手伝いをいたします。

この記事を書いた人
クーシーブログ編集部
1999年に設立したweb制作会社。「ラクスル」「SUUMO」「スタディサプリ」など様々なサービスの立ち上げを支援。10,000ページ以上の大規模サイトの制作・運用や、年間約600件以上のプロジェクトに従事。クーシーブログ編集部では、数々のプロジェクトを成功に導いたメンバーが、Web制作・Webサービスに関するノウハウやハウツーを発信中。
お問い合わせはこちらから
Web制作デザイン、丸ごとお任せ
お問い合わせする
デザイン:ピョータント